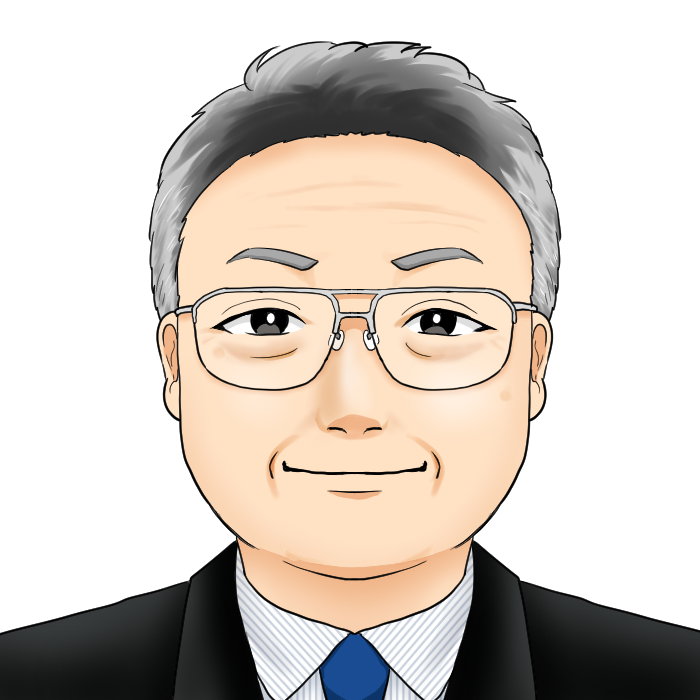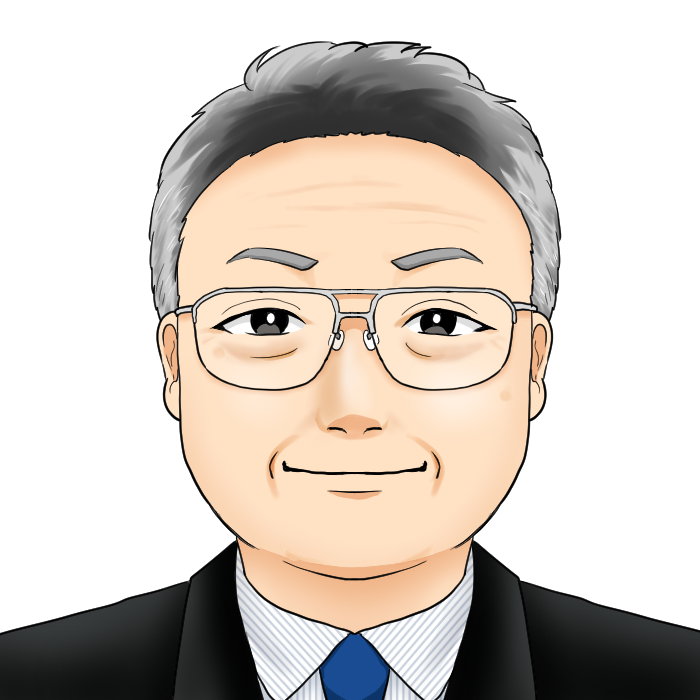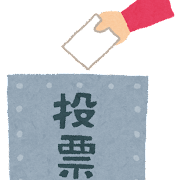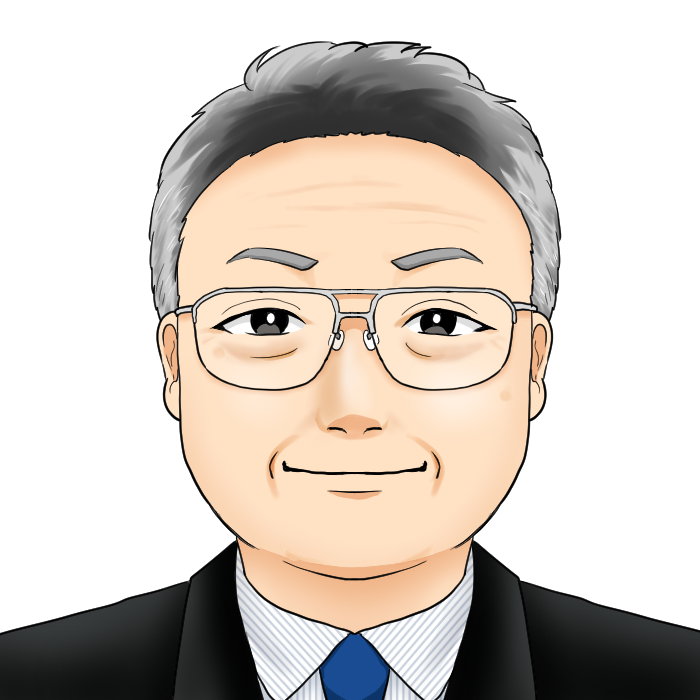🌸 10分集中してやれば、確実に実力がアップします(できる!)。

伊藤博文(いとうひろぶみ)のイラスト
1 憲法の発布(はっぷ)
1882年 伊藤博文らは、ヨーロッパに派遣され、ドイツやオーストリアの憲法を学んだ。
伊藤博文が中心となって、憲法の草案を作成し、枢密院(すうみついん)で審議を進めた。
1889年2月11日 天皇が国民にあたえるという形で、大日本帝国憲法が発布された。
憲法では、天皇は国の元首(げんしゅ)として統治する、と定められた。
また、帝国議会は、皇族・華族などによって構成される貴族院と,公選議員で組織される衆議院との2院からなった。
憲法に続いて、刑法、民法や商法なども制定され、地方政治の制度も整備された。
1890年 明治天皇によって、教育勅語(きょういくちょくご)が出された。
→ 忠君愛国の道徳が示され、教育の柱とされた。
2 議会の開設(かいせつ)
1890年 第1回衆議院議員選挙が行われた。
選挙権があたえられたのは、直接国税15円以上を納める25歳以上の男子 - 有権者は総人口の1.1%(約45万人)にすぎなかった。
日本は、アジアで最初の近代的な立憲制の国家となった。
◎ 基礎・基本の用語
〇 伊藤博文(いとうひろぶみ)- ヨーロッパに派遣され、君主権の強いドイツの憲法を学んだ
〇 大日本帝国憲法(だいにっぽんていこくけんぽう)- 1889年2月11日に公布
〇 帝国議会(ていこくぎかい)- 大日本帝国憲法に基づく議会
〇 貴族院と衆議院(ぎぞくいんとしゆうぎいん)- 華族・皇族などと選挙で選ぶ
〇 直接国税15円以上納める25歳以上の男子 - 第1回衆議院議員選挙の選挙権
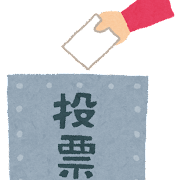
投票箱のイラスト(選挙)
♢ 選挙の歴史クイズに挑戦
👉初めての衆議院選挙では,たくさん税金を納めている25歳以上の男女に選挙権があった 次から選びなさい。
A ホント B ウソ
👉初ての衆議院選挙では,投票するとき,自分の名前も書かないといけなかった 次から選びなさい。
A ホント B ウソ
👉昔の選挙には立候補の制度がなかった 次から選びなさい。
A ホント B ウソ
※ 出典 『選挙の歴史クイズに挑戦! 福岡市』から
答えは最後に
☆ ふり返り
◇ ①~⑤に当てはまる言葉を答えなさい。(⑤は数字)
1882年 (①)らは、ヨーロッパに派遣され、ドイツやオーストリアの憲法を学んだ。
1889年2月11日 天皇が国民にあたえるという形で、(②)が発布された。
(③)は、皇族・華族などによって構成される(④)院と,公選議員で組織される衆議院との2院からなった。
選挙権があたえられたのは、直接国税(⑤)円以上を納める25歳以上の男子 - 有権者は総人口の1.1%(約45万人)にすぎなかった。
💮 答え
① 伊藤博文(いとうひろぶみ)
② 大日本帝国憲法(だいにっぽんていこくけんぽう)
③ 帝国議会(ていこくぎかい)
④ 貴族院と衆議院(ぎぞくいんとしゆうぎいん)
⑤ 直接国税15円以上納める25歳以上の男子
👉初めての衆議院選挙では,たくさん税金を納めている25歳以上の男女に選挙権があった
答え A ホント B ウソ
👉初ての衆議院選挙では,投票するとき,自分の名前も書かないといけなかった
答え A ホント B ウソ
👉昔の選挙には立候補の制度がなかった
伊藤博文は、初代内閣総理大臣として知られる政治家ですが、実は合計4回内閣総理大臣になっています。1000円札の肖像にもなりました。これで基礎学力バッチリです。