🌸 15分集中して身近な生活の場面について考えてみましょう!

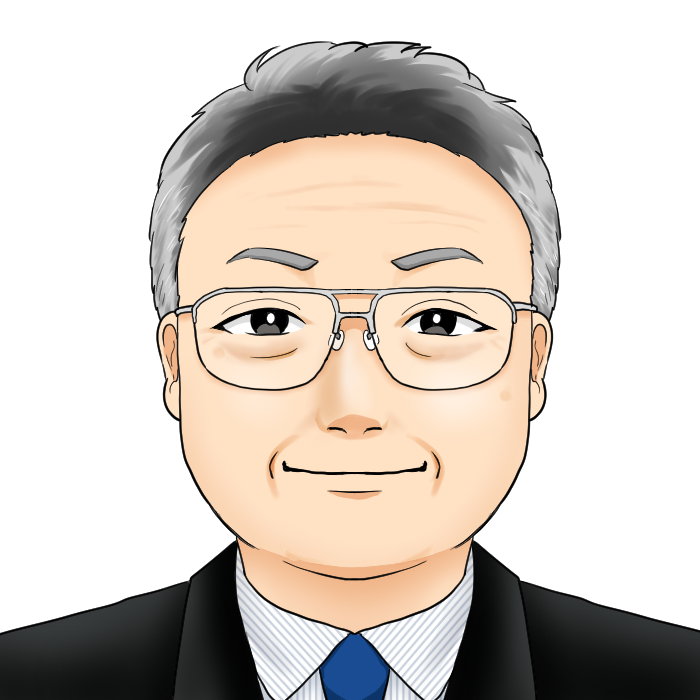
労働者の 権利をわかりやすく解説します。
目次
1 なぜ働くのか
働く目的は何か聞いたところ、
「お金を得るために働く」と答えた人の割合が53.7%、
「社会の一員として、務めを果たすために働く」と答えた人の割合が14.0%、
「自分の才能や能力を発揮するために働く」と答えた人の割合が7.8%、
「生きがいをみつけるために働く」と答えた人の割合が19.8%となっています。
(出典 : 内閣府「国民生活に関する世論調査」(平成27年6月調査))
〇 働くことに関する用語の意味
- 労働者とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいいます。(労働基準法第9条)。
- 使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいいます。(労働基準法第10条)。
- 賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいいます。(労働基準法第11条)。

2 労働三法
わが国には、労働者を守る様々な法律がありますが、その中でも基本となるものが
- 「労働基準法」
- 「労働組合法」
- 「労働関係調整法」です。
これら3つの法律を、「労働三法」と呼んでいます。
① 労働基準法(労基法)は、労働関係において労働者を保護するため、
労働関係の基本原則と賃金、労働時間等の労働条件について、最低の基準を定めたものです。
② 労働組合法は、日本国憲法第28条の
「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」
という規定を受けて、
労働者が使用者と対等な立場で交渉できるようにするため、
次に示す「労働三権」を具体的に保障するものです。
- 団結権 = 労働者が、労働条件の維持・改善について使用者と対等な立場で交渉するために、労働組合を結成する権利
- 団体交渉権 = 労働者が使用者と団体交渉をする権利
- 団体行動権(争議権) = 労働者が使用者に対し、労働条件の維持・改善を求め団体で行動する権利
③ 労働関係調整法は、労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防又は解決するものです。
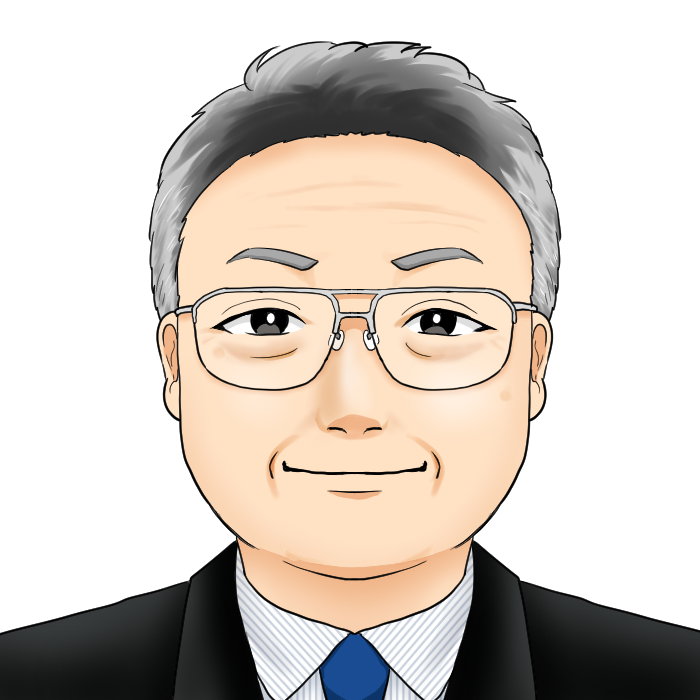
さあ、基礎・基本の用語をしっかり覚えましょう。
◎ 基礎・基本の用語
〇 労働基準法(ろうどうきじゅんほう)- 労働条件について最低の基準を定めたもの
〇 労働組合法(ろうどうくみあいほう)- 労働三権を具体的に保障するもの
〇 労働関係調整法(ろうどうかんけいちょうせいほう)- 労働争議を予防又は解決するもの
〇 団結権(だんけつけん)- 労働組合を結成する権利
〇 団体交渉権(だんたいこうしょうけん)- 労働者が使用者と団体交渉をする権利
〇 団体行動権(だんたいこうどうけん)- 労働条件の維持・改善を求め団体で行動する権利
👉厚生労働省は、労働時間、休憩、休日について、次のように法定の制度としています。
- 使用者は、原則として、1日に A 〇時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。
- 使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は B 〇時間以上の休憩を与えなければいけません。
- 使用者は、少なくとも毎週 C 〇日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。
上の〇に当てはまる数字を答えなさい。
A ( )時間 B ( )時間 C ( )日
☆ ふり返り
◇ ①~⑤に当てはまる言葉を答えなさい。
1 (①)法は、労働関係において労働者を保護するため、労働関係の基本原則と賃金、労働時間等の労働条件について、最低の基準を定めたものです。
2 (②)法は、労働者が使用者と対等な立場で交渉できるようにするため、労働三権を具体的に保障するものです。
3 (③)法は、労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防又は解決するものです。
4 (④)は、労働者が、労働条件の維持・改善について使用者と対等な立場で交渉するために、労働組合を結成する権利です。
5 (⑤)は、労働者が使用者と団体交渉をする権利です。
6 団体行動権は、労働者が使用者に対し、労働条件の維持・改善を求め団体で行動する権利です。
💮 答え
① 労働基準法(ろうどうきじゅんほう)(労基法)
② 労働組合法(ろうどうくみあいほう)(労組法)
③ 労働関係調整法(ろうどうかんけいちょうせいほう)
④ 団結権(だんけつけん)
⑤ 団体交渉権(だんたいこうしょうけん)
⑥ 団体行動権(だんたいこうどうけん)(争議権)
👉厚生労働省は、労働時間、休憩、休日について、次のように法定の制度としています。
- 使用者は、原則として、1日に A 〇時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。
- 使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は B 〇時間以上の休憩を与えなければいけません。
- 使用者は、少なくとも毎週 C 〇日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。
上の〇に当てはまる数字を答えなさい。
答え A ( 8 )時間 B ( 1 )時間 C ( 1 )日
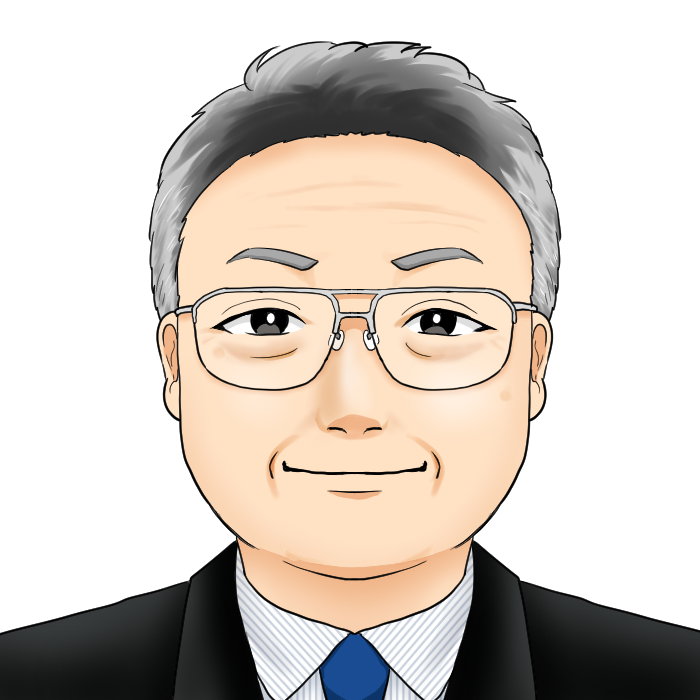
これで基礎学力バッチリです。






