
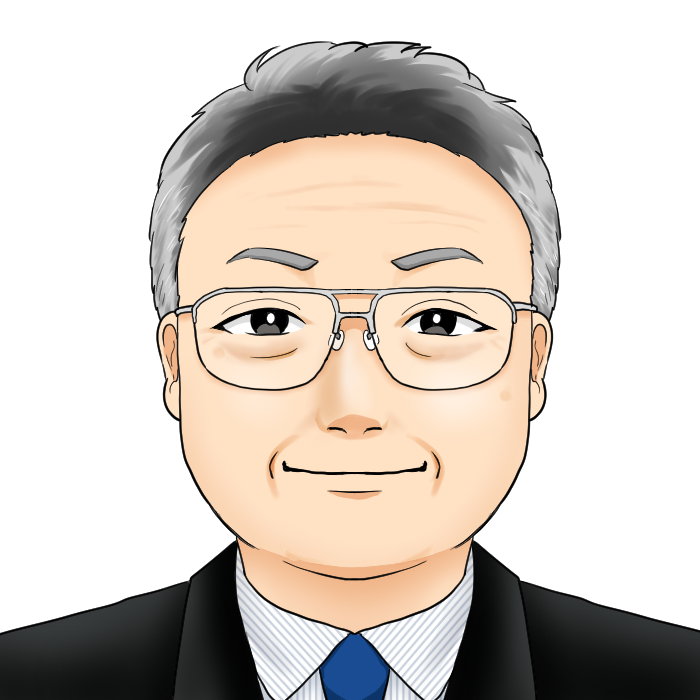
今日は、オザビエル(私)が、
心理学者、千葉大学名誉教授
多湖 輝(たご あきら)さんの著書
『楽老のすすめ』から 実践していきたい
「幸齢者mind」をお届けします。
目次
1 「立つ鳥、後を濁さず」
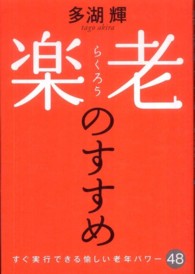
「立つ鳥、後を濁さず」とは、日本人の美徳の一つです。
改めて説明するまでもないかもしれませんが、
たとえば引っ越し、たとえば転職というように、
元いた場所から立ち去るときには、
後の人の手を煩わせないように、
すっかりきれいにしておく、ということです。
その空極は、やはり、人の死でしょう。
そこでいつも想い出すのが、「さよなら、さよなら」の決め台詞で
有名だった映画評論家の淀川長治氏です。
淀川氏とは、生前、何度かお話させていただいたことがあります。
たいていの映画は否定しなかった淀川さんが、
きっぱりと、「嫌いです」とおっしゃった映画があります。
それは、渡辺淳一さんのベストセラー小説を映画化した「失楽園」でした。
映画の名誉のためにも言っておきますが、
淀川氏が好まなかったのは筋書きではなく、
最後に男女が心中を遂げるのが室内だった、という点でした。
淀川氏は、毎晩、枕元に葬式代を置いて寝ていたほどの人です。
生涯独身だった淀川氏が、最後に住むことに決めたホテルも、
「エレベーターに棺桶が入るかどうかで決めた」
とおっしゃっていたほどですから、自分が死んだ後のことを、
人一倍気にかけていらっしゃったことがうかがわれます。
そんな淀川氏にとって、
たとえ映画の中とはいえ、発見されにくい室内で、
自殺をする男女の無神経が信じられなかったのでしょう。
淀川氏のこの話は、
死ぬことは、まさに今、いかに生きるかを考えることにつながる、
ということを教えてくれています。
死から考えると、生が見えてくるということです。
死ぬときの自分は、どうありたいか。
いわば死という最終地点を定め、
生はそこに向かっていく過程だと考えると、
人生に対する見方もぐっと変わってくるはずです。

2 最高の有終の美を飾る
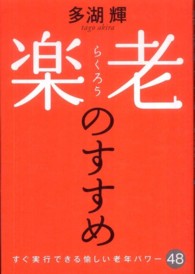
この先、何十年も残されていない老年人生ならなおのこと、
死ぬときの自分の理想像から逆算して、
それまでをどう生きるかを考えておくべきです。
死と言うと、暗いイメージがつきまといますが、
私はそれは違うと、と思います。
今言ったように、
死を考えることが、より深く生を考えることにつながり、
より深く生を考えることが、人生をより充実させることは間違いないからです。
必ず訪れる死までを、どのように生きるか、それは人それぞれでしょう。
しかし、最期が醜くては、それまでの輝かしい人生も台無しです。
病気や介護で、周囲の手を煩わせてしまうのは仕方ありません。
それでも老年人生を楽しく生き抜き、
そして自分が死んだ後には、
極力、世話になった人たちの手を煩わせない。
そんな潔い死にざまを見せられたら、
老年人生は、最高の有終の美を飾ることができる、と思うのです。
3 今日の金言 多湖 輝(たご あきら)
「立つ鳥、後を濁さず」とは、日本人の美徳の一つです。
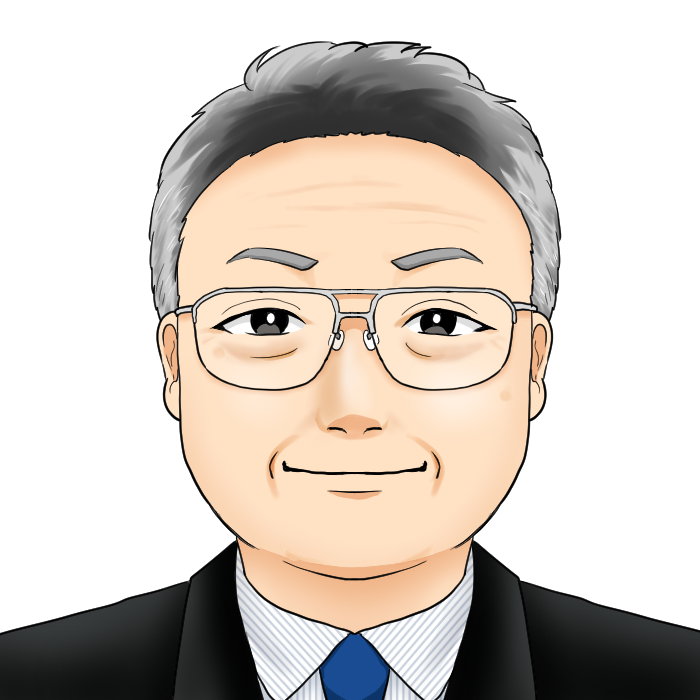
死を考えることが、より深く生を考えることにつながり、
より深く生を考えることが、人生をより充実させる。
自分の寿命予定は〇歳。
それから逆算して、残り〇〇年、〇〇〇日。
これからますます、周囲の人に少しでも喜ばれる存在となり、
充実した生き方をしていきたい。
そして、世話になった人たちの手を煩わせないで、
最高の有終の美を飾ることができるように、
「少しずつ、少しずつ」準備をしておきたいと思います。





