
出典:画像 知っておきたい認知症の基本 政府広報オンライン
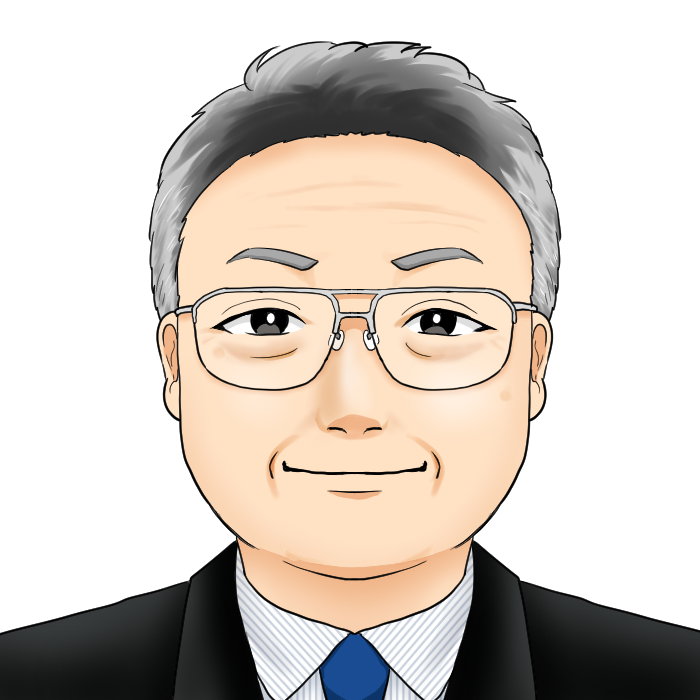
今日は、オザビエル(私)が、
NHKガッテン!2020年4月号 (発売日2020年2月15日)
総力特集「認知症が怖くなくなる予防と介護の新対策」から学んだ
実践していきたい
「幸齢者mind」をお届けします。
目次
1 認知症のリスクを減らせる方法

回答者 鳥羽研二さん(東京都健康長寿医療センター理事長)
世界が注目する最新知見!「認知症予防」の現在
1 WHOによる「予防ガイドライン」
2019年にWHO(世界保健機関)は、「認知症予防ガイドライン」を発表しました。
- 運動
- 地中海式食生活
- 社会的活動
- 禁煙など
2 WHOに医学雑誌『ランセット』では「認知症の35%は防げる」
信頼度の高い医学雑誌として知られる『ランセット』の発表では、認知症の発症リスクを高める9つの要因を列挙。
これらをすべてクリアできれば、認知症の35%は防ぐことが可能であるとしています。
◉ 9つの認知症リスク要因
人口寄与割合
【小児期】
1 教育機関の短さ 8%
【中年期】
2 高血圧 2%
3 肥満 1%
4 難聴 9%
【高年期】
5 喫煙 5%
6 うつ 4%
7 運動不足 3%
8 社会的孤立 2%
9 糖尿病 1%
予防可能な認知症 合計35%
認知症の「予防」と「共生」は、矛盾しない
「認知症の予防」には、次の3つの段階があります。
[一次予防]は、発症リスクを減らす生活をして、認知症にかからないようにする段階
[二次予防]は、同居の人たちの協力を得ながら、認知症を早期発見、早期治療して生活機能の低下を防ぐ段階
[三次予防]は、同居の人たちの協力をもとに、認知症がさらに重症化していくのを防ぐ段階
人生100年時代と言われる今日、誰にとっても認知症は他人事ではありません。
ですから現在、予防と合わせて重要視されているのが、
- 「認知症になったとしても、幸せに暮らせる環境」
- 「認知症とともに生きる社会」
をつくることなのです。
「若返っている」日本人、発症率低下の兆しも?
今の日本の60代は、歩くスピードも衰えていませんし、運動週間のある人も増えています。
誰もが、認知症にならずに済む可能性は持っています。
でも大事なことは、認知症に「備える」ことです。「認知症になったら終わり」という捉え方をしていたら、認知症への不安は、いつまでたっても解消されないのではないでしょうか。
2 認知症の予防

回答者 島田裕之さん(国立長寿医療研究センター老年学・社会科学研究センター長)
『無理なく楽しく』が基本、『仲間』がいればなおよし
現時点では、「これをすれば確実に認知症が予防できる」明確な明確な研究結果はありません。
ただ運動が脳の機能の保持に役立ちそうだという研究結果は数多くあります。
ここでは、運動への向き合い方について、よりおすすめできる方法をお伝えしたいと思います。
- 長く続けられること
- 自分が楽しいと思えること
- 体と頭を同時に使うこと
- 仲間とともに楽しめること
体と頭を同時に使う「コグニサイズ」の効果
私たちは、65歳以上の軽度認知障害をもつ高齢者100人に集まってもらい、研究を行いました。
運動教室で体と頭を同時に使う「コグニサイズ」を行うグループと、教室で健康講座のみ受けるグループに分け、10か月後に認知機能や脳の萎縮度を比較しました。
すると前者のほうが記憶力の向上が著しく、脳の萎縮の進行は抑えられていることがわかりました。
つまり、体と脳を同時に使うことが、認知症のリスクを下げるのに効果的だと考えられます。
たとえばゴルフも、条件を満たす運動のひとつ

ゴルフを習慣的にしていない高齢者106人を対象に、ゴルフと認知機能の関係を研究しました。
ゴルフをする人・しない人の2グループに分け、前者はゴルフの実技練習に加え、頭を使うスコア計算の講習などもあわせて実施。
それを6か月間行った結果、前者のほうは、記憶力などの認知機能が向上していたのです。
3 コグニサイズ

もっと手軽にできる<その場運動>もおすすめ
有酸素運動と同時に知的活動を行うと、認知機能の低下予防に効果があることがわかつています。
その研究結果をもとに、手軽にできるエクササイズとして考案されたのが「コグニサイズ」です。
少し間違うぐらいが、ちょうどいい。上手にできたら、新しいチャレンジへ!
STEP1 ➧ 1人で行う「コグニサイズ」
足踏み + 3の倍数で拍手
背筋を伸ばし、足踏みをしながら、声を出して数を数えます。
ただし、3の倍数になったら拍手をします。
このときは、声をださないようにします。
※ ももはできるだけ高く上げます。
※ 100まで続けましょう。
※ 慣れてきたら、5の倍数、7の倍数にするなど、数字を変えて挑戦を。
STEP2 ➧ 仲間といっしょに「コグニサイズ」
足踏み&手拍子 + 足し算
背全員で足踏みや手拍子をしながら、1、7、13………というふうに、1から始めて、6を足した数字を順番に声を出します。
※ 立ってしても、座ってしてもいいです。
※ 慣れてきたら、100から6を引いた数を順番に声を出します。
※ さらに、足し算、引き算の数字を変えて行います。
4 絵本の読み聞かせ

出典:画像 子どもと本をたのしもう どうして読み聞かせを続けるの? 彦根市

回答者 鈴木宏幸さん(東京都健康長寿医療センター研究所研究員)
絵本の「読み聞かせ」などの知的活動も予防効果が高いことがわかってきました。
「読み聞かせ」の効果を科学的アプローチで検証
私が所属する研究チームが「絵本の読み聞かせ」に注目したのは、シニアを中心とした世代間交流が目的でした。
ところが、認知症予防効果について検証してみると、「記憶力が向上し、海馬の萎縮が抑えられる」という期待以上の結果が得られたのです。
活動の内容としては、まず「絵本読み聞かせ講座」としてインストラクターの指導を受けます。
そこで、読み方のコツ、発声などについて学習。
その後、子どもを対象とした読み聞かせ会や、障がい者施設などで定期的に実演を行います。
「知的刺激+社会参加」で自然に活動量も増える
読み聞かせのメリットは、
- 知的活動によって「認知的予備力」が高まる
- 新しい体験が、脳のネットワークを強化する
- 身体的な活動量も増える
- 仲間がいると長く続く
- 社会貢献ができる
参加者から「この年になって人生に花が開いたよう」などという言葉を耳にすると、いくつになっても活動の場があることの大切さを実感します。
「囲碁」や「アート」などの知的活動にも注目
囲碁に関して興味深いのは、ネット上で対戦した人は、囲碁をしない人よりも認知機能が向上しましたが、囲碁教室で対面して行った人のほうが、さらに検査の成績がよかったことです。
5 「アルツハイマー型」認知症は、よく寝て防ぐ!

睡眠時間はアミロイドβの排出時間
アルツハイマー型認知症は、「アミロイドβ」というたんぱく質が排出されず、脳に蓄積して起こると考えられています。
近年、アミロイドβの産出量は、健康な人もアルツハイマー型認知症の人も変わらないことがわかってきました。
つまり、その発症にはアミロイドβの「排出量の低下」が関係していると考えられるのです。
では、どうすればアミロイドβが排出されるか。その確実な方法のひとつが「睡眠」と言われています。
即実践!アミロイドβを一掃する快眠生活
ある研究では、アルツハイマー型認知症になるリスクを低くするには、
- 睡眠時間は6~8時間
- 1日30分の昼寝
が効果的だというデータがあります。
ある研究では、睡眠の質がよい人ほどアミロイドβがよく排出されていました。
睡眠の質を上げるオススメ「快眠術」
- 日中に光を浴びる
- 日中に運動をする
- 食事時間で1日のリズムを作る
- 緑茶、コーヒーは、就寝4時間前まで
- 「最初の90分間」深く眠る
6 今日の金言
「絶対に認知症にならない」という予防法はないこと。
「発症リスクを減らす」あるいは「先延ばしにする」方法はあるということです。
鳥羽研二さん(東京都健康長寿医療センター理事長)
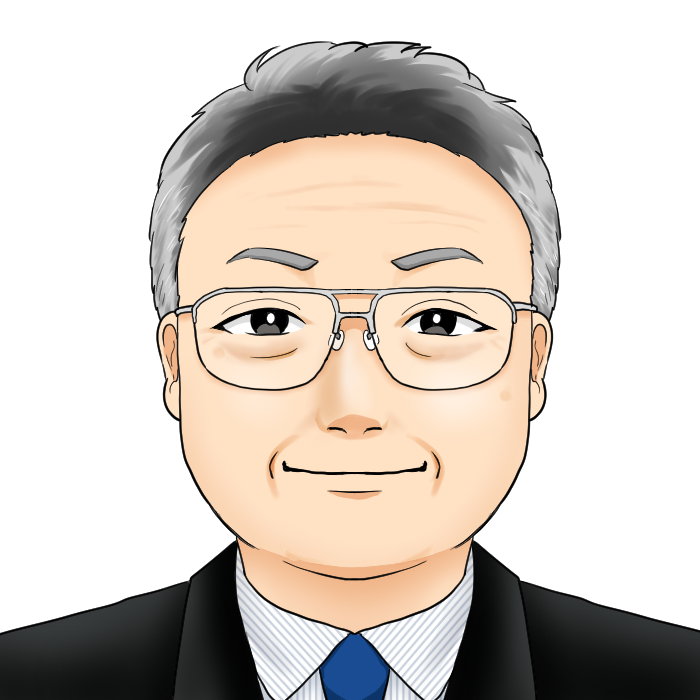
オザビエル(私)も、健康長寿を願っていますが、
認知症の発症リスクは高まらざるを得ません。
現時点でわかっている≪本当のところ≫を
学ぶことができました。
認知症の予防を心がけ、
健康長寿を延ばしていきましょう。
出典 NHKガッテン! 2020年4月号 (発売日2020年2月15日)総力特集「認知症が怖くなくなる予防と介護の新対策」 出版社 主婦と生活社 画像はヤフー検索から






